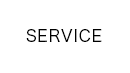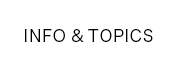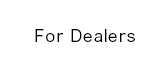自動運転のある世界
2015年5月20日 公開
自動車業界トピックス
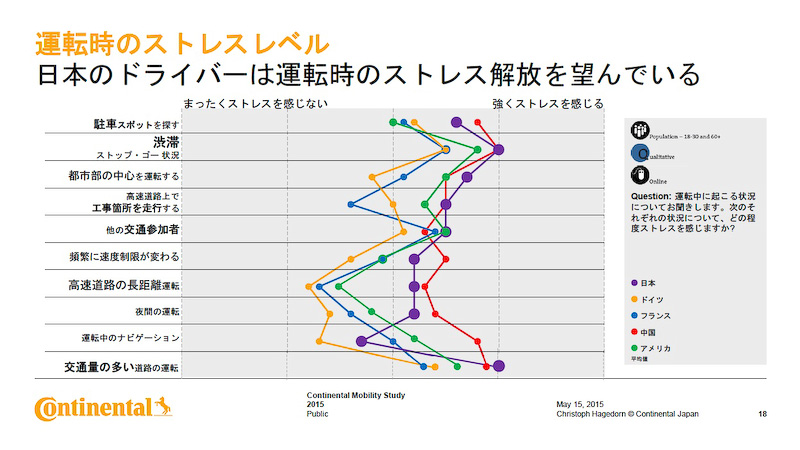 (出展:Car Watch http://car.watch.impress.co.jp/docs/news/20150520_702761.html)
(出展:Car Watch http://car.watch.impress.co.jp/docs/news/20150520_702761.html)
一方、自動運転が普及することはまさにパラダイムシフトとも言える大きな変化を社会にもたらすことが別の記事で提示されていたのを見つけました。
自動運転車で失業するのは運転手だけ、と思うのは甘い(GIZMODO)
もし車が完全に自動運転できる世界が来たら。 保有すること自体を目的(=ステータス、趣味)としたごく一部の車を除き、全てのクルマは社会の共有インフラになってしまう、という予測が提示されています。 鉄道やバスのように駅や停留所まで行かなくても、ドアtoドアで人や荷物を運んでくれる自動運転車のサービスが登場すれば、高い維持費や初期投資をしてまで車を保有したいと思う人は(そのコストに見合う所有理由や意欲がある人を除き)いなくなるでしょう。 ますます都市部に人口が集中する中で、その都市に占める道路や駐車場のスペースは有限です。いずれ車の保有台数にはリミットがかけられます。香港など国土の狭い国や都市では、ナンバープレートに高い税金をかけて車の保有を制限する仕組みがすでにあります。自動運転技術は、そうした動きにさらに拍車をかけるでしょう。 そこで問題となるのが、「自動車を沢山作って沢山売る」ことで利益を出している自動車メーカーの立ち位置です。 総数としての自動車の台数は減るわけですから、彼らのビジネスモデルはいずれ破たんします。最初は安全のため、商品としての魅力向上の為の自動運転技術や機能が、回り回って自分の首を絞めることになる・・・ 必ずこうなるとは言えませんし、世界的に見れば自動運転技術にそぐわない道路や国の方が多いわけですが、主要マーケットである先進国や新興国は急速に自動運転技術を持った車が普及することになるでしょうから、早い遅いの程度の差こそあれ、未来図はほぼ固まっているような気がします。 「車は所有しなくても、使うときだけその時間を買えばいい」 機械化やIT化が労働集約型産業の飛躍的な効率化を促したように、自動車の個人(法人)所有が当たり前であることを前提とした様々な産業は、こうした変化への備えをそろそろ考え始めてもいいのかもしれません。Koji Yamanaka